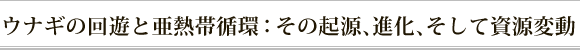ウナギの回遊と亜熱帯循環:その起源、進化、そして資源変動
青山 潤(東京大学海洋研究所)
ウナギの産卵場
降河回遊魚であるウナギ属魚類は、海で産卵する。ウナギ Anguilla japonicaの産卵場調査は1930年代に始まったが、最初のレプトセファルスが採集されたのは、1967年のことである。その後、計4回の大規模な研究航海の末、1991年7月、ついに白鳳丸が全長10 mm前後のウナギのレプトセファルス約1000尾を採集し、マリアナ諸島西方海域が産卵場であることを明らかにした。研究はさらに継続され、それまでに得られた全てのレプトセファルスの分布、体サイズ、海流や海底地形から、ウナギの産卵場は西マリアナ海嶺北緯15°前後の3つの海山(スルガ、アラカネ、パスファインダー)であると推定された(海山仮説)。また、採集されたレプトセファルスの孵化日解析から、ウナギは産卵期各月の新月の日に同期して一斉に産卵することがわかった(新月仮説)。
世界のウナギ属魚類で初めて、産卵の時間と場所を厳密に絞り込んだこれら仮説を基に実施した2005年6月の白鳳丸研究航海の結果、新月である7日に産卵場と推定されていたスルガ海山の西約100kmの地点で、孵化後2日齢のプレレプトセファルス約400尾を採集することに成功した。海流の平均流速と日齢および卵期の長さから逆算するとこれらのプレレプトセファルスは、新月の4日前にスルガ海山近傍で産卵されたものであることがわかった。これらのことはウナギ産卵場に関する上記2つの仮説を満たしており、ウナギの産卵地点をピンポイントで突きとめたといえる。
ウナギの回遊生態
1991年以降実施されてきた白鳳丸によるウナギ産卵場調査航海は、ウナギ仔魚の回遊生態の概略を明らかにしている。それによると、レプトセファルスは1日に0.5mmずつ成長しながら北赤道海流で西へ輸送され、やがて黒潮に乗換え北上する。この際、貿易風によるエクマン輸送が重要な役割を果たしていることもわかってきた。貿易風が強すぎると、レプトセファルスは黒潮へ取り込まれる前に北上しすぎて黒潮反流の渦の中にとりこまれてしまい、逆に弱すぎた場合は、南下するミンダナオ海流に取り込まれ、本来ウナギの分布しないフィリピン南部やインドネシアへ輸送され、無効分散(死滅回遊)になってしまう。この貿易風仮説はシラスウナギの接岸量を予測する唯一の仮説として注目されている。また、エルニーニョによって産卵場の塩分フロントが南北に移動することでレプトセファルスの輸送環境が大きく変化し、シラスウナギの接岸量が変わるという「エルニーニョ仮説」も提出されている。孵化後150日前後で全長約60mmに到達すると、レプトセファルスは変態を開始し、約3週間かかってシラスウナギになる。すなわち、黒潮を離脱したシラスウナギは東アジアの河口を目指し、孵化後180日前後で河口域に到着するのである。
熱帯ウナギの産卵回遊生態
2000年1-3月に実施した白鳳丸による調査航海、また2001年5月と2002年9-10月に行ったインドネシア科学院LIPIのバルナジャヤVIIによる調査航海において、スラウェシ島周辺海域のウナギレプトセファルスを採集した。これら3航海では、熱帯ウナギ7種計96個体(白鳳丸15個体;7個体は太平洋西部海域、バルナジャヤVII2001年52個体、2002年29個体)のウナギレプトセファルスを得ることができた。これらの研究航海は、初めての本格的な熱帯ウナギ産卵・回遊生態調査であり、数多くの貴重な知見をもたらした。まず、2000年2月には、フィリピンとインドネシアの間に位置するセレベス海で、ふ化後2-3週間と考えられる8.5および13.0mmのA. borneensisと12.3mmのA. celebesensisが採集され、これらの産卵場がセレベス海にあることが初めて明らかになった。さらに、2001年5月にはスラウェシ島北部の半島に囲まれるトミニ湾でも13.0-48.9mmのA. celebesensis 36個体が採集され、セレベス海と地理的に隣接するトミニ湾にも産卵場があることが示された。セレベス海やトミニ湾のA. borneensisやA. celebesensisの産卵場は、これらの成育場の目と鼻の先に位置している。これまで、ウナギは大産卵回遊をする魚と考えられていたが、どうやらこれは温帯に生息する一部の種についてのみいえることのようである。
ウナギ属魚類の遺伝的集団構造
一般に、数千キロ規模の分布域を持つ海産魚や淡水魚は、複数の地域集団に分化していることが多い。しかし、北大西洋のヨーロッパウナギやアメリカウナギおよび太平洋のウナギでは、その広大な分布域に比較して種内の遺伝的変異がきわめて少ないことが知られている。太平洋からインド洋の熱帯域に生息するオオウナギには5つの地域集団が知られているものの、その他の温帯種はすべて基本的に単一集団を形成している。これは、産卵場が限定され、ふ化した仔魚が受動的に輸送されるウナギの特異な回遊生態によるものと考えられる。すなわち、回遊に利用する海流の速度が早いため、回遊経路となるベルトコンベアーの規模が大きく数千キロ程度の分布域なら一つの繁殖集団でカバーしてしまうのである。一方、A. celebesensisが同一種であるにもかかわらず、地理的に数十キロしか離れていないセレベス海とトミニ湾に産卵場を持つことが明らかになった。これらの海域は半閉鎖的であり、特にトミニ湾は最深部で4000m以上あるものの、湾口部は数百メートルの浅い海峡となっている。このため、両海域にはそれぞれ独自のベルトコンベアーが形成され、隣接して生息する本種個体群が遺伝的に異なる集団を形成している可能性がある。すなわち、熱帯ウナギは回遊や集団構造などの生態学的特性において、これまで多くの知見が得られている温帯種とは大きく異なるものと考えられる。
ウナギの回遊の起源と進化
海産のウナギ目魚類の中で唯一ウナギのみが降河回遊性の生活史を持つことから、この生活史特性はウナギ属が派生したときに獲得されたものと考えることができる。Gross (1987)によると、通し回遊は海と川の基礎生産力の差によって進化してきたとされている。すなわち、より生産性の高い環境にたまたま移動したものが、生産性の低い従来の環境に残ったものよりも多くの子孫を残し繁栄することにより、偶発的な回遊が定型化し、規則的な回遊になったと考えられる。最も古い系統と考えられるA. borneensisやその他の熱帯ウナギが局所的な回遊を行っていることから、熱帯に派生したウナギの祖先種も、生育場の近くに産卵場を持ち小規模な回遊をしていたものと推察される。当時、地球の南北方向の小さな温度勾配に起因するゆっくりとした海流に輸送されていたレプトセファルスは、それほど高緯度まで達していなかったものと考えられる。やがて寒冷化の時代になると、温度勾配の形成とともに表層大循環はスピードを増し、さらに大陸の分裂移動にともなって環赤道海流は分断され、すべての海流が赤道付近から南北にそれていくようになる。これにともないウナギはより高緯度まで輸送されるようになったと推察される。おそらくあるものは死亡して無効分散になったが、あるものはそこで生き残り、成熟に達することができた。しかし、今日のサケが海で成長しながら産卵場を川に残しているように、繁殖に関する特性は保守的であるため、熱帯にある産卵場を高緯度域まで動かすことはできない。このため、高緯度域に流れ着いて成長した親ウナギは、産卵のために遥か何千キロも旅をして熱帯まで帰っていかなくてはならなかった。それらの一部が、たまたま産卵に適した海域に到達し、卵を生むことに成功する。産卵場の位置によっては、多くのレプトセファルスが外洋など成育場とならない場所へ運ばれ死滅してしまったであろう。しかし、親ウナギが数千キロ離れた成育場と安定した海流によって結ばれる産卵場を見いだした時、そこに大規模な回遊経路が成立したのである。すなわち、今日認められるウナギの大回遊は、海流によって高緯度へ序々に拡がりつつある成育場と熱帯に残された産卵場との間に形成され進化してきたものと推察することができる。
ウナギの資源
1970年代以降、ウナギ資源は右肩下がりに減少を続けている。その減少要因については、乱獲、河川や河口の環境悪化、さらに地球温暖化による影響などが上げられている。しかし、原因の特定はおろか、資源変動の実態すら明らかになっていないのが現状である。特に、資源の管理や保全といった観点から、ウナギを特殊な存在としているのは「降河回遊」である。外洋でふ化した仔魚は、東アジアの数カ国にまたがる成育場へ加入する。この際、海洋構造の影響により成育場内のある場所には大量に接岸し、ある場所にはほとんど接岸しないといった多寡が生じる。さらに、成育場となる河川・水系の環境によって、加入したウナギ個体群の性比やサイズ組成、成熟年齢が大きく変化することが知られている。すなわち、同一の産卵場で生み出されたにもかかわらず、ウナギは加入した成育場によって、量的にも生物学的にも大きく異なる個体群に分断されるのである。こうして、それぞれの成育場で成長・成熟したウナギは、再び外洋の産卵場で出会い、次世代を生み出す。このような特異なウナギ資源の管理・保全のためには、まず、広大な成育場と数千キロにおよぶ回遊経路で、何がおきているのかを知る必要がある。